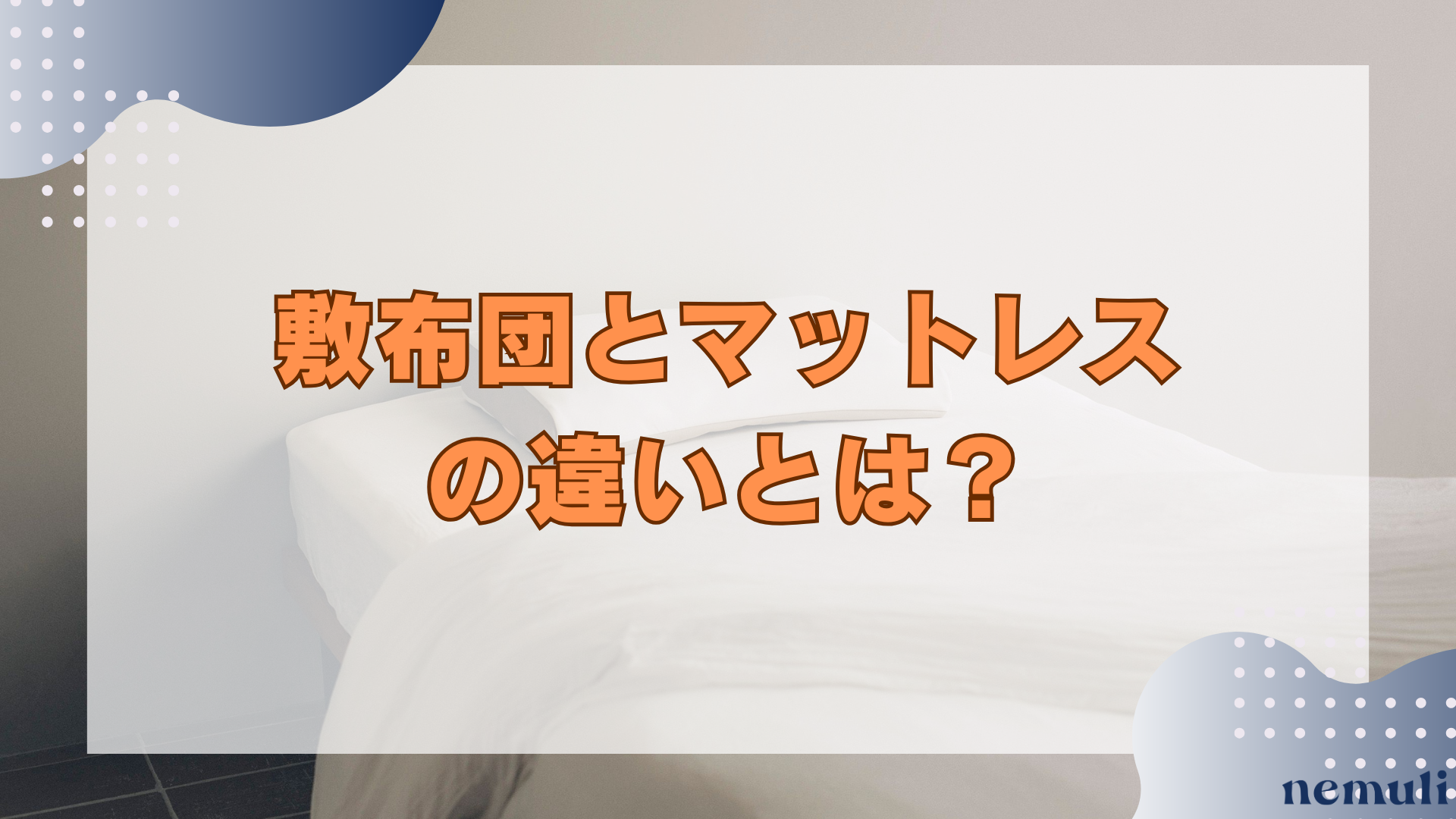
敷布団とマットレスの違いとは?フローリングで使う方法やおすすめまでを徹底解説!
MENU
『敷布団とマットレスってなにが違うの…?』 『敷布団と
マットレスどっちがおすすめ…?』
と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、敷布団とマットレスの違いから、フローリングで使う注意点や選び方のポイントまで解説します!
\この記事のまとめ/
- 敷布団とマットレスの違い|メリット・野球を解説
- 敷布団とマットレスをフローリングで使う注意点
- 敷布団とマットレスの選び方のポイント|4つのポイントに注目
この記事を読んで、マットレスに関する悩みを解消し、より快適な夜を過ごしましょう!

敷布団とマットレスどっちがおすすめ?

マットレスと敷布団どっちがおすすめか、以下の3つの場所によって変わります!
- 畳の上で寝たいなら敷布団
- 床で直接寝たいなら折りたたみマットレス
- ベッドフレームの上で寝たいならベッドマットレス
では、ひとつひとつ見ていきましょう!
畳の上で寝たいなら敷布団
和室など畳の上で寝たい方は、敷布団がおすすめです!
包み込んでくれるような柔らかさがある敷布団は畳の落ち着いた雰囲気と相性がよく、心地よく眠りにつけることができます。
腰痛や底つき感が気になる方は、敷布団用のマットレスを敷いてクッションを確保しつつ、考え方が向上します。
注意点としては、カビが発生しないように可能であれば毎日畳から敷布団を離し、畳の湿気を逃すことです。
また、敷布団の中に溜まっている湿気を乾かすために、最低でも1週間に一度は天日干しが必要です。
太陽の光で住んでいたダニも駆除できるので、衛生面も良くなります。
その際、軽くはたいと思いますが、厚みが回復してより長くお使いいただけます。
床で直接寝たいなら折りたたみマットレス
フローリングの上で寝たい方は、折り畳むためのマットレスがおすすめです!
床に敷き続けていると湿気はどんどん増えて、すぐにカビが発生してしまいます。
湿気を乾かすためには、床からマットレスを離しておく必要があり、その際折りたたみできるマットレスが便利です。
しかし、折りたたみできるマットレスは比較的薄いものが多く、厚みが足りないと、底つき感を感じやすかった、身体の圧力分散が早くて、快適な感想が得られません。
さて、マットレスの上にマットレストッパーを踏まえて、姿勢を確保して見方が良くなります。
ベッドフレームの上で寝たいならベッドマットレス
ベッドフレームの上で寝たい方は、ベッドマットレスがおすすめです!
ベッドマットレスとは、ベッドフレームの上にあることを想定されたマットレスです。
一般的なマットレスは、上にマットレストッパーなどを重ねて使いますが、ベッドマットレスは厚みが20cm以上あるものが多く、単体での使用が可能です。
床とその間空間が確保できるので、湿気によるカビも発生しにくく、基本的に敷きっぱなしでも問題はありません。
ただし、物が見つかると湿気の避難道が狭くなり、マットレスにカビが生じやすくなります。
また、汚れを防ぐため、隠れるかプロテクターを使用しましょう。
ーーーーーー
以上が、マットレスと敷布団どちらがおすすめでしたか!
考えと以下の通りです。
- 畳の上で寝たいなら敷布団
- 床で直接寝たいなら折りたたみマットレス
- ベッドフレームの上で寝たいならベッドマットレス
続いて、敷布団とマットレスの違いをご紹介します。
敷布団とマットレスの違い

次に、敷布団とマットレスの違いについて解説します!
- 敷布団
- マットレス
では、ひとつひとつ見ていきましょう!
敷布団の特徴
敷布団は一般的に、畳やフローリングなどの床に直接敷いて使用します!
睡眠ときのみ床に寝て、起床後は寝て部屋の隅やクローゼット・押し入れに当たることを想定しておりますが、一般的にはマットレスに比べて比較的と考えが薄いものが多くあります。
中素材は木綿や羊毛(ウール)など昔ながらの素材として知られていますが、現在ではウレタンや合成繊維が一般的に使われています。
▼敷布団の特典
敷布団は押し入れやクローゼットに収納でき、移動がしやすいので部屋の掃除も簡単にできます!
天日干しやクリーニングを出すなどお手入れも簡単なため、衛生的に使い続けられます。
素材や構造などの種類が豊富で、予算に合わせた価格帯から幅広く選べる点もメリットです。
また敷布団は高低差が少ないため、寝相の悪い方や小さい子どもでも安心して寝られます。
▼敷布団の野球
敷布団のままの扱いは、敷いたときに通気性が良くなり、湿気がたまりやすくなる点です!
ベッドマットレスのように普段敷いたまま使用する場合は床に直置きせず、すのこベッド・除湿シートを下に敷く、布団乾燥機を使うなど、除湿対策が必要です。
また敷布団はマットレスに比べて厚みが薄いため、あえて敷布団を使用すると床付き感が強くなりやすい点も普及しています。
そして床との距離が近いため、冬の時期は床からの寒さが身体に伝わりやすい点も対処すると言えます。
マットレスの特徴
マットレスを指すのは主にベットフレームに乗せて使用するベッドマットレスです!
また、敷布団の下に敷いて使用する和式マットレス(アンダーマットレス)、敷布団と同じような用途で使用できるマットレスもあります。
ベッドマットレスは中素材にや密度の高いウレタンを使用していることが多く、硬さ・反発性で身体を支え、厚みがあるため床付き感がありません。
和式マットレス(アンダーマットレス)・マットレスは敷布団と同じように上げ再生や収納も考慮され、三つ折り・四つ折りなど、透ける工夫がされている商品が多くあります。
▼マットレスのメリット
ベッドマットレスは中素材がコイルスプリングの場合のやさのこベッド状態と組み合わせて使うと、通気性がよく、湿気がこもりにくいのがメリットです!
一般的に耐久性が高く、中素材によっては10年程度使える商品もあります。
また敷布団のように上げ録画の必要はなく、毎日保存する手間がありません。
マットレスは敷布団より厚みがあるため、床からのほこりを吸い込みにくい点もメリットです。
また厚みがあるため床付きで冷えがなく、ふかふかとした体重を感じやすい点も魅力です。床からくる底感が少なく、睡眠中に身体が冷えるのを避けられます。
立ち上がる際の負担がないため、敷布団に比べて、寝起きの身体への負担がかかりにくい点もメリットです。
▼マットレスの治療
ベッドマットレスの治療は、敷布団に比べて価格が高くなりやすい点です。
購入費用だけでなく、廃棄する際の費用も高額になる傾向があります。
ベッドマットレスはベッドの上に常に敷いたままになるため、部屋にベッドを置けるスペースが必要です。
またベッドマットレスは一般的に大きく重量があるため、敷布団のように手軽な手入れが面倒で、日干しも頻繁に気がかりではありません。
マットレスの裏を日陰で干して、風通しを良くすることが重要です。
ーーーーーー
以上が、敷布団とマットレスの違いでした!
考えと以下の通りです。
- 敷布団の特徴|床に直接使用する
- マットレスの特徴|ベットフレームにおいて使用する
続いて、敷布団とマットレスをフローリングで使う際の注意点をご紹介します。
敷布団とマットレスをフローリングで使う際の注意点

敷布団とマットレスをフローリングで使う際の注意点について解説します!
- ダニ・カビ
- 腰への負担
- 寒さ
では、ひとつひとつ見ていきましょう!
ダニ・カビ
布団に湿気がこもると、床にダニやカビが発生しやすくなります。
人間は寝ている間にコップ1杯相当約200mlの汗があるため、毎日フローリングに水分が付着しています。
フローリングのダニやカビの対策、防ダニ性能の布団や定期的な換気、カビ対策ができるすのこの使い方がおすすめです!
腰への負担
フローリングに柔らかい敷布団やゆったりのマットレスのみを使うと、腰部分へたりが早く、腰に負担がかかるため注意が必要です。
敷布団やマットレスは、ほど良い硬さの反発力と抑圧のあるものを選ぶ、腰への負担を軽減することが重要です。
寝返りを打ちやすい硬さがあると、腰に辛さを感じにくいので、体格や体重に合わせて敷布団やマットレスを選びましょう!
寒さ
冬のフローリングは冷気を強く感じやすいため、敷布団やマットレスを使う際は、冷気対策しましょう。
通気性がよい敷布団・マットレスの場合、冬は暖かいシーツや敷きパッドを組み合わせ、床からの冷気も考慮した防寒対策を行いましょう。
ウレタンのマットレスは断熱効果に優れているため、保温面を考慮した選択としてもおすすめです!
ーーーーーー
以上が、敷布団とマットレスをフローリングで使う際の注意点でした!
考えと以下の通りです。
- ダニ・カビ
- 腰への負担
- 寒さ
続いて、敷布団やマットレス選びのポイントをご紹介します。
敷布団やマットレスの選び方のポイント

敷布団やマットレスの選び方のポイントについて解説します!
- 体圧分散性で選ぶ
- 反発力で選ぶ
- 清潔性で選ぶ
- 耐久性で選ぶ
では、ひとつひとつ見ていきましょう!
体圧分散性で選ぶ
一般的に、立ったときの姿勢を横に、まっすぐな寝姿勢が、よい寝姿勢と落ち着きます。
体圧分散性のある敷布団は、肩や腰回りなど負荷がかかる部分の圧力を分散し、まっすぐな寝姿勢へと考えます。
肩や腰への負担を軽減したい人は、好みはありますが、体圧分散性バランスのよい硬さの敷布団やマットレスを選びましょう!
反発力で選ぶ
回復力は、まともなものを選びましょう!
反発力が強すぎると体との間に隙間ができ、体重のかかる部分に負担がかかりやすくなります。
反対にやわらかすぎると体重のかかる部分が深く沈み、寝姿勢も崩れ寝返りを打ちにくいため注意が必要です。
ウレタンや樹脂素材を使った高反発の敷布団やマットレスは、身体をしっかり支えて寝返りをサポートできるのでおすすめです。
清潔性で選ぶ
敷布団やマットレスの汚れやにおい、菌の繁殖を防ぐためには、お手入れしやすいものを選びましょう!
就寝中の発汗量はコップ1杯分であり、汗は敷布団に吸収され、においや菌が繁殖する原因になります。
湿気手入れはダニやカビの温床となるため、敷布団であれば干しやすさ、側地での洗濯慎重など、自宅でしやすいものがおすすめです。
耐久性で選ぶ
敷布団は一般的に3~5年、マットレスは約10年前後が耐久年数とあります。
とりあえず使うためには、耐久性の高い素材を選びましょう!
敷布団に使われる天然素材には羊毛・綿があります。羊毛はへたりにくい、綿素材はへたものの打ち直しに対応できます。
敷布団・マットレスに使われる化学素材はウレタン・樹脂・合成繊維などがあります。
ウレタンは密度が高いほどへたりにくい特徴があり、樹脂・合成繊維も耐久性を追求した商品が多くあります。
ただ行ってしまうと元に戻らないため、買い替えが必要になる点に注意が必要です。
ーーーーーー
以上が、敷布団やマットレス選びのポイントでした!
考えと以下の通りです。
- 体圧分散性で選ぶ
- 反発力で選ぶ
- 清潔性で選ぶ
- 耐久性で選ぶ
続いて、敷布団としても使えるおすすめのマットレスをご紹介します。
敷布団としても使えるおすすめのマットレス

敷布団とマットレスの違いを解説してきましたが、『結局どれがいいの…?』という方には、三つ折りタイプのマットレス『nemuli The FUTON』がおすすめです!
日本人の睡眠習慣に合わせて作られた、軽いのにしっかりとした高反発素材で身体を支える究極のマットレスです。

『nemuli The FUTON』は、日本人の睡眠習慣に合わせて作られた三つ折り仕様のマットレスです。
一般的な敷布団と同じように扱える手軽さに加え、体圧分散性・通気性・軽量設計にこだわって開発しました。
独自のウレタン凹凸構造による優れた体圧分散性で、軽さと薄さを追求しながらも、しっかりとした高反発素材で底感の無いところが上がるような実力さが魅力です。
また、利便性を追求し、移動時に片手で扱えるようにマットレス本体に取り扱えます。
通気性の良いウレタン製でマルチな使用シーンを想定しているため、現在使用しているマットレスに重ねて、マットレストッパーとしても、直接床やベッドフレームに敷いてマットレスとしてもお使いいただけます。
完全オンラインで購入ができるため、すぐに時間がかからない方や自分にあった寝具が欲しい方にも最適です。
マットレス選びで間違えない方や、より重視にこだわりたい方にもおすすめですよ!
まとめ|どれが快適ならマットレスを選びましょう!

今回は、敷布団とマットレスの違いから、フローリングで使う注意点や選び方のポイントまで解説しました!
\この記事のまとめ/
- 敷布団とマットレスの違い|メリット・野球を解説
- 敷布団とマットレスをフローリングで使う注意点
- 敷布団とマットレスの選び方のポイント|4つのポイントに注目
、敷布団かマットレスどっちが適当で決められないという方は、もしベッドマットレスを選ぶのがおすすめです。
ベッドフレームが必要ですが、基本的に敷き続けることができるので手入れが少なくて済み、質の高い睡眠が取りやすいからです。
寿命も敷布団より長く、買い替えの頻度も減って財布にも優しいです。
マットレス選びに悩んでいる方は、本記事を参考にしてみてください!

